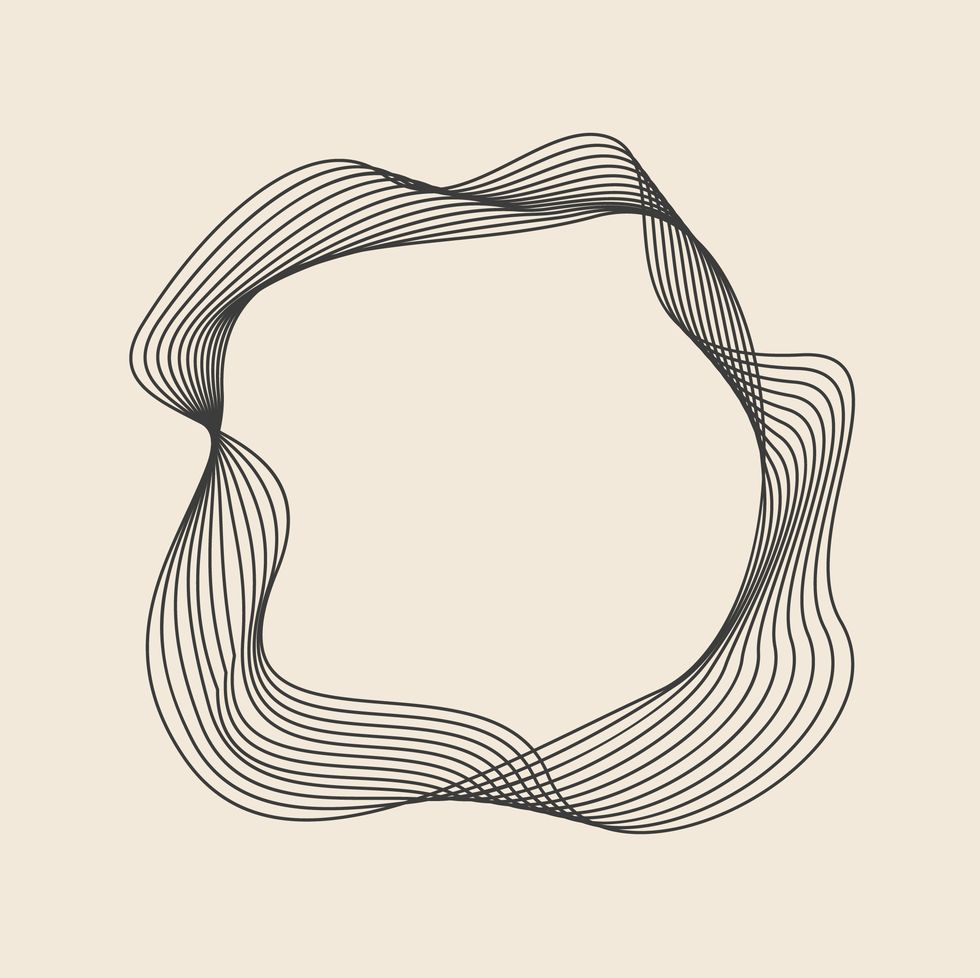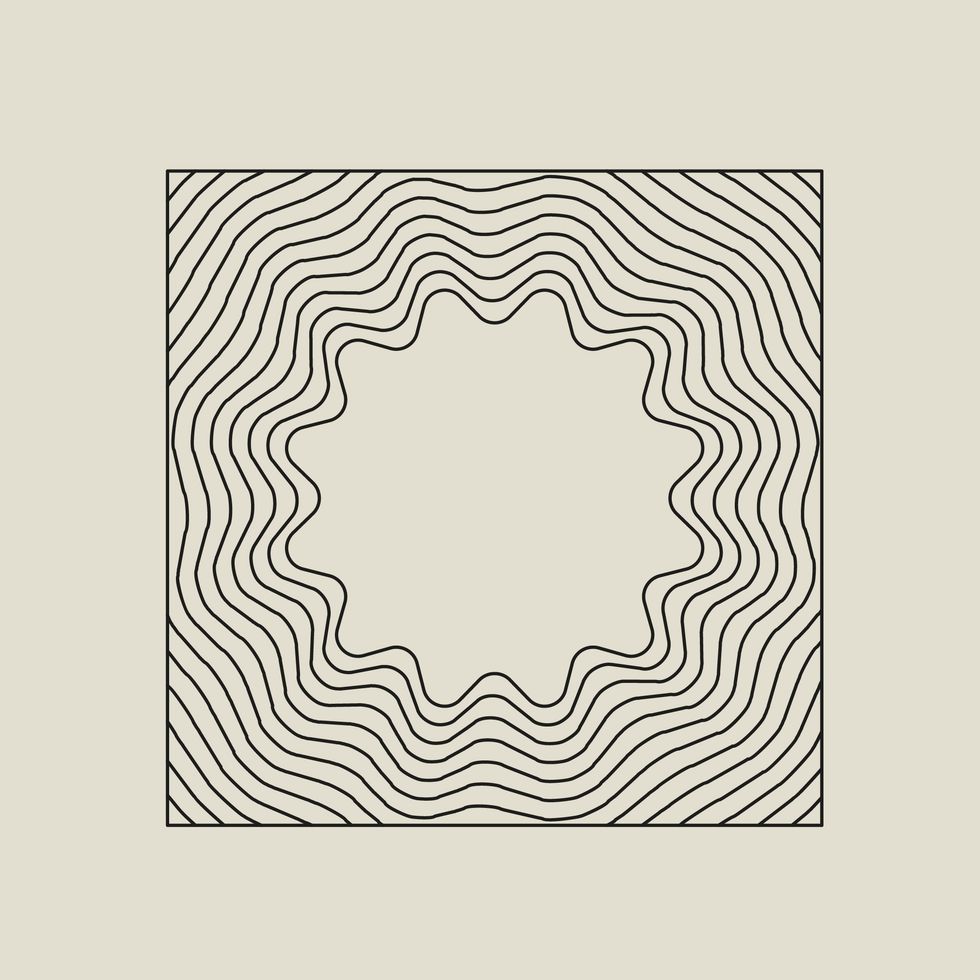LGBTQIA+当事者の中でも、特にトランスジェンダーの方を取り巻く環境の厳しさが社会に響くようになり、権利向上に向けた動きが起こるようになってしばらくが経ちます。
トランスジェンダーというと、「出生時とは逆の性で生きている人のこと」と考えられがちですが、実際にはトランスジェンダーかつノンバイナリーやXジェンダーを自認する方たちもたくさんいます。
2020年に出版された『誰かの理想を生きられはしない――とり残された者のためのトランスジェンダー史』の「はじめに」では、「女性/男性に当てはまらない性」「二元的ではない性」を自認するトランスジェンダーである吉野 靫さんの人生が綴られています。
性別二元論(人間の性を女性、男性の2つのみで定義する社会規範)が適用される社会は、「二元的ではない性」を自認する人にとって生きづらさを感じさせるもの。
本記事では、トランスジェンダー、ノンバイナリー、クィアの当事者の視点から、現在の社会制度への違和感について吉野さんに伺いました。
吉野 靫さん
学生時代は立命館大学自治会で学費値下げやジェンダー課題に取り組む。2006年、身体改変に伴う医療事故をきっかけに、トランスジェンダーに関する論文執筆や企画開催を開始。
性別二元論にとらわれていたことも
――まずはじめに、これまでの活動について教えて下さい。
私は18歳のときにカミングアウトしました。現在はノンバイナリー系トランスジェンダー/クィアと名乗っていますが、当時はFTM(Female to Male:出生時に割り当てられた体の性が女性であるものの、男性のジェンダーアイデンティティを表現するトランスジェンダー)と名乗っていたんです。
大学で過ごしているなかで、トイレの使いづらさや通称名を使用したいこと、明らかに不要な性別欄をなくして欲しいなど、生きづらさを感じるようになって。そこで大学の学生自治会を訪ね、活動家としての生活が始まりました。
学生自治会では、大学と交渉をしたり、学習会の開催、新入生に向けた冊子の発行などといった活動をしていました。またセーファーセックスやDV、セクシャルハラスメントなども広くテーマとして扱い、2004年には全国でおそらく初めて、学生団体主催でレインボーパレードを実施しました。
学生時代に広くそういった活動をして、多くの人と関わり勉強を進めるうち、自分が性別二元論にとらわれていたことに気付いたんです。
18歳の頃は「女性性に疑問を抱いたならば、男性に着地するしかないのでは」と思っていたのですが、そうではないことに気付き、「女性と男性どちらにも帰属しないタイプのトランス」と表現するようになりました。ただ、自分の中での考えが変わった一方で、身体に対する違和は残ったままでした。
2003年から通っていた大阪医科大学で、手術をすることになったのが2006年。そこで医療事故が起こってしまい、その後は提訴して裁判闘争をせざるを得なくなりました。そのときは文学研究科の大学院に進学していたのですが、原告として裁判をしながら生活を送らなければいけないことを考えると、国からもらえる研究助成金など、現実的な戦略として「トランスジェンダー研究」を始めざるを得ないような感じで。
そこから、『誰かの理想を生きられはしない――とり残された者のためのトランスジェンダー史』に掲載したような論文執筆も開始しました。
女性や男性に帰属感のないトランスジェンダーとして
――吉野さんが自認される「ノンバイナリー系トランスジェンダー」「クィア」について、あらめてご自身がしっくりくる表現で教えてください。
最近になって、日本にも「ノンバイナリー」という言葉が入ってきました。“バイナリー(二元的)でない”ことを一言で表現できて便利だなと思い使っていますが、その言葉にすごく自分のアイデンティティを投影しているかというと、そうではなくて。
自分のジェンダーのありようを表現するよりかは、「性別二元論に対抗するというスタンス」を示した方がしっくりくると思っています。なので、「女性や男性に帰属感のないトランスジェンダー」という説明的な名乗りを選んでいます。
「クィア」は、私にとって“規範的でないジェンダーアイデンティティに確信を持ち、二元的な性別や異性愛、家父長制などで構成された社会から逸脱する”という政治的な立ち位置を表せる言葉なので、20歳ぐらいの頃から一貫して自分の核となっています。
――ご自身の性自認に至ったきっかけは何でしたか?
私の場合は多くのFTMの方が語るような「子どものころからペニスが欲しかった」や「生理が嫌で泣いた」といった典型的なエピソードがあるわけではありません。
あるいは「女性を好きになったから、自分は男なんだと思った」といった異性愛的な語りの感覚もありませんでした。
私はジェンダー(性役割)への拒否感・違和感と身体への違和感が、非常に混ざり合って自覚したような感じがします。もちろんジェンダーへの疑問や抵抗感を感じる女性はたくさんいると思うのですが、私の場合は環境を整えたり色々と勉強を進めていったりしても、どうしても胸がない方がいいという確信だけは揺らがなかった。だから結果的には、身体改変もしたという感じです。
トランスジェンダーを排除したい側に「性役割への忌避感からトランスと言っているだけでは」と言う方がいますが、正直私はそこまで厳密に区分け出来るものではないんじゃないかと思います。
結果的に身体を変えてはいるけれども、出発点は“身体違和”というよりも、“ジェンダー(性役割)違和”だったという方もいるのではないかと。
身体を変えた結果その人が生きやすくなっているのであれば、それを現象としてトランスジェンダーと呼ぶのかもしれない。けれど厳密に「その人がトランスか否か」を分ける事項として厳密な“身体違和”があるのかっていうと、そうとは限らないのではないかと私は思っています。
社会に対する違和感
テレビなどのメディアで目にするトランスジェンダーの人々は、FTMやMTF(Male to Female:出生時に割り当てられた体の性が男性であるものの、女性のジェンダーアイデンティティを表現するトランスジェンダー)の方が多く取り上げられており、そうではない当事者もいると知る人はまだ多くないかもしれません。
しかし実際はXジェンダーやノンバイナリーを自認する人もおり、トランスジェンダー全員が“逆の性”への同化を望んでいる訳ではないと吉野さんは言います。
――特例法制定※により、社会のトランスジェンダーのイメージが「全員が逆の性への同化を望んでいる」などといった偏ったものになっていると思います。
吉野さんはこういった風潮についてどうお考えですか。
※性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
そもそも2022年の現在も「性同一性障害」という言葉が通用してしまっていること自体が少し特殊であり、日本の状況がガラパゴスであると表現される要因の一つかなと思います。やはり医療ベースの“病気”としての理解が先に進んでしまったことが、日本の特殊なところの一つかと。
2001年に放送されたドラマ『3年B組金八先生』のエピソードや、2000年代に発売された自伝、マスメディアが“悲劇的な性同一性障害者像”を多くの人に訴求してしまった結果、「これだけ苦しんでいるのだから戸籍を変えさせてもいいんじゃないか」「病気だからしょうがない」といった理解の形になってしまっていると思うんです。
たとえば、「可愛いかった女の子が、ひげを生やした筋骨隆々の男性になりました」というように、分かりやすく二元化されたトランスジェンダーの姿は、マジョリティ側に「なんだ、これなら“本物”の女性・男性と変わらないじゃないか」という安心感や受け入れやすさをもたらします。
制度面でも人々の意識の面でも、あくまで「現行の制度・これまで信じてきた女性男性の姿を揺るがさない」当事者が求められていましたし、メディアもそういう人を取り上げた。昔からXジェンダー的・ノンバイナリー的な性の表し方をしている人はいたのに、そういった人々は可視化されにくかったのです。
特例法制定のときは、「戦略としてここで法律を通しておかないと、次にいつ成立させられるのか分からない」という状況だったそうで、子なし要件(当時は「現に子がいないこと」)についてなどとても激しいやり取りがあったと聞きます。しかし当時の状況として、どうしても多数派が受け入れやすい条件で譲歩するしかなかったし、当事者の表象もバックグラウンドのストーリーも、“理解されやすい形”で提示するしかなかった。
それが、シスヘテロ社会に適応するために、当事者の中に「パス(世間から自分の望む性別の人として認識される)している方が優位」という規範をもたらすことにもつながったのだろうと考えています。
当事者だってジェンダーを変えているだけで「普通」の人間なわけですから、さまざまな人がいるのは当たり前です。ですが何か一芸に秀でているとか、外見が優れているとか、特徴的な当事者だけをメディアに出していたのも問題だと思います。ひと昔前なら“ゲイ=オネエ”といったような先入観・イメージがありましたけれど、それと同じでどこか特殊な存在であるという印象も抱かせていったと思いますね。
社会が変えていくべきこと
――吉野さんが日常生活を送る上で、「こんなところが変わればより生きやすくなるのにな」と思う点はありますか?
大学時代、トイレの使用や集団検診のときの配慮、通称名使用、書類の性別表記など、大学時代の活動によって変化はありましたが、「個別対応に限られる」という限界も感じていました。
またそれらは私のような「行動できるタイプの当事者」がいたから出来たことであって、そういった個人の力に依拠する形での“場当たり的な対応”は変えていくべきだと思います。制度として広く色々なタイプのマイノリティに対応出来るようにしていかなきゃいけないと思うんです。
今はそこそこの数の大学でダイバーシティ・インクルージョン宣言や、そういった方針だけは発表されていますが、まだ形式的な部分もあるような気がします。たとえば、トランスジェンダーの学生が通名を使用する際に診断書を求めたり、保護者の同意書を求めたりと、当事者に負担を課すケースは未だに聞こえてきます。
特例法制定のときも「性同一性障害の典型例」のような当事者が多くヒアリングされましたし、企業にも学校にも言えることですが、代表的なケース・分かりやすいケースさえカバーできれば、それで良しとしてしまうところがあると思います。細かい点の調整は、いつもその制度からこぼれた側が説明したり、要求したりしなければならない。ですから、いかに最初から広い範囲をカバー出来るような制度設計にしておくかだと思うんですね。
また相談窓口などができても、実際に対応する人がどれだけ勉強しているのか、信用に足るのかは、私は常に疑問に思っていました。すでに雇われている人が何回か研修を受けて兼任することもあります。企業や学校がきちんと予算をつけて専門家を雇うなど、「声明を出した」「学長がこう発言した」だけでなく、やはりお金をかけて変えていかないといけないと思います。
――性別二元論が適用される世の中に対し、どのようにアクションをしていけば良いと思いますか。
たとえばヒゲを生やしたFTMが出産をするなど、“異質”ととらえられるような存在って、始めはびっくりしたり戸惑ったりがあると思いますが、FTMの人が出産をすること、生まれ持った身体を変えている人がいること、そういったことを全部含めて慣れていくのが重要だと思います。
生まれ持った性を変える人や、二元的な性以外を名乗る人に脅威を感じるとしたら、そういった人々がここ数年で突然世の中に出てきたような感覚でいるからだと思います。少し前まで性的マイノリティの人々は社会と折り合いをつけるため、自分の中で調整せざるを得なかったですし、自分のセクシュアリティを明らかにすることなく亡くなっていった人たちもいます。
今は、そういうことを明らかにする人が徐々に可視化されている段階であって、存在としては昔からいたわけです。それでもマジョリティの生活は問題なく回ってきましたし、これからもその生活が変わったり、権利が剥奪されたりすることはないのです。
そして、「極めて多様な個人によって構成されているのが“社会”である」という当たり前の認識をして頂きたいです。そして逆の立場になったと想像してみてください。他者が介入してきて「お前の在り方を変えろ」または「本当は存在しないはずだ」と言われること。自分のいないところで、自分の存在が許されるか否か勝手に議論されること――。どれだけ理不尽に思うだろうかと。
ですから、あくまで「慣れてね」というのは、極めて穏当で現実的な方法だろうと私は思うのです。
コミュニティに対する違和感
ーーノンバイナリー系トランスジェンダーと自認されている吉野さんですが、トランスジェンダーコミュニティにおいて生きづらさを感じたことはありますか。
2000年代の初めは「半端なトランスお断り」という言葉がウェブサイトに書いてあったりしました。身体を大きく変えている当事者が集まっていることが多く、それ以外は排除されるのではないかと怖かったし、「二元的な性への埋没を目指す人」以外は少し入りづらい雰囲気がありました。
けれど関西と関東では、コミュニティの傾向が少し違っていて。東京ではL、G、B、Tに分かれたコミュニティがあったけれど、関西にはそこまで人数が多くないからみんないっしょくたに集まっていた。“ミックス”の状態になると色んな人が入ってきやすかったし、クィア文化が育まれていくという点がありました。私は何も知らず関西に進学しましたが、それが私にとっては正解だったかなと思います。
存在を尊重すること
――最後に吉野さんのようなノンバイナリー系トランスジェンダーの方、その他「二元的な性」以外を名乗られている方たちに対し、サポート出来ることは何でしょうか。
これはもう10数年言い続けていることで、性的マイノリティに限った話ではないのですが、「相手の名乗りを尊重しきる」以外にないです。
トランスフォビアの人たちからしょっちゅう聞くのは、「トランスジェンダーの定義・根拠を示せ」ということ。根拠も何も、逆を言えば「あなたがシスジェンダーの女性・男性として生きている根拠はなんですか」ということなんですよ。だから相手の「こう呼んで欲しい」「こういうふうに扱って欲しい」という要望を“受け止めて尊重する”のが、すべての前提だと思います。
その上で、その人の望む生活がすべて実現できるかというと、それはそれで調整が必要になります。けれどもその存在を“尊重すること”は出来るわけですよ。
他には私の個人的な経験から言えば、励ます・寄り添うよりかは、不当・不正、理不尽であることに、一緒に怒ってくれる人の存在が支えになったかなというのはあります。
マイノリティ側が面倒ごとを抱えたり、理不尽な目にあっているときには、可能な範囲で良いので「ここは引き受けるよ」と言ってくれること。一緒になって怒ってくれること。署名したり、意見を送ってくれたりすること。
“アライ(LGBTQIA+を理解し、支援する人のこと)”という名前だけ掲げたり、プライド月間にただレインボーでアピールしたりという瞬発力よりも、面倒ごとを持続的に一緒に背負ってくれることが良いんじゃないかと思います。
プロフィール
吉野靫(ヨシノユギ)
クィア、トランスジェンダー。立命館大学先端総合学術研究科修了。学生時代は、学費値下げ運動とジェンダー・セクシュアリティ問題への取り組みに傾倒。2007年から2010年まで身体改変にまつわる医療訴訟を経験。著書に『誰かの理想を生きられはしない――とり残された者のためのトランスジェンダー史』(2020年、青土社)、2022年はこれまで『新潮』3月号、『GQ Japan』6月号、『エトセトラvol.7』等に寄稿。
猫と暮らす。 香港の古いカンフー映画、韓国映画が好き。中島みゆきとザ・クロマニヨンズをよく聴く。ヨガ歴13年。