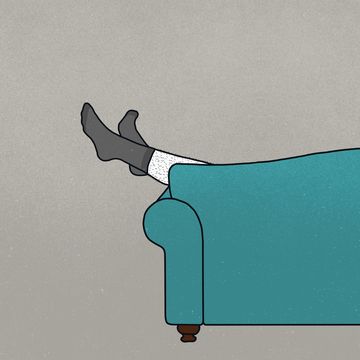近年問題視される、ヘルスケア領域におけるジェンダーバイアス。イギリスでは過去10年間に、ジェンダーバイアスが原因で誤った診断や治療を受けた結果として心臓疾患で死亡した女性の数が8000人を超え、また、脳腫瘍の診断が遅れるケースは、男性より女性のほうが2倍多いと推定されています。
他にも、心肺蘇生法が必要な状況で死亡する確率は女性のほうが男性より高いこと、さらに、がんの種類によっては診断が下されるまでに女性のほうがより長く時間がかかる傾向があることがわかっているとか。
では、こうしたジェンダーによる“違い”は具体的にどのようにして生じるのでしょうか? また、状況を改善するにはどのような解決策があるのでしょうか? この記事では、実際に病気の正しい診断が遅れた経験をもつ女性2名の体験談や、イギリスで起こっている議論や問題の背景について<コスモポリタン イギリス版>からご紹介します。
※この記事は、海外のサイトで掲載されたものの翻訳版です。データや研究結果などはすべてオリジナル記事によるものです。
症状を訴えても“大げさ”“ストレス”と言われ…
最初にご紹介するのは、なかなか正しい診断をしてもらえず、結果として脳腫瘍の治療が遅れたというキャサリン・グラドウィンさんの体験談。
脳腫瘍のために複数回の手術を受けたキャサリンさん。彼女は最初の手術の約8カ月前にも病院を受診していましたが、そのとき彼女が「絶対にどこか悪いはずなんです。もっとよく診てください」と懇願しても、医師は「ストレスが溜まっているんじゃないでしょうか?」と言うだけだったと言います。
キャサリンさんの脳腫瘍は、何人もの医師が「問題ない」と存在を否定しつづける間に体内で大きくなり、発見があと半年遅ければ失明するおそれもあったと言います。しかし彼女は2年近くの間、医者たちからストレスが原因だとかうつ病だとか、早期の更年期障害だとか言われて、抗うつ薬やパニック発作を抑える薬、生理を起こす薬などを処方されていたのです。
もちろんケースによって状況は様々で、誤診の原因を特定するのは不可能ですが、「もし男性が同じ症状を訴えていたら、もっと早く正しい診断がされていたのではないか」という問いについては考えてみるべきではないでしょうか。
ここで、歴史を15、16世紀まで遡ります。当時、医師たちが研究のための解剖に用いたのは死刑に処された犯罪者(主に男性)の遺体で、薬などもそうした研究にもとづいて開発されました。それから3世紀が経っても、女性が医者になることはまだ許されもせず、女性が訴える様々な不定愁訴は、不安感からむくみにいたるまで“ヒステリー”という一言で片づけられがちでした。
今の時代、ヒステリーという病名で正式な診断が下されることはありませんが、<コスモポリタン イギリス版>読者の74%は、医療従事者に「(症状に)大げさに反応している」と受け取られたことがあると回答。また、2015年のイエール大学の研究によると、多くの女性、特に若い女性は、心臓発作の疑いがあっても“心気症(しんきしょう)”と思われるのではないかと懸念し、医療機関を受診するのが遅くなったり、そもそも受診を避けてしまったりする傾向があるといいます。
医学研究の領域では、男性の体で学ぶことが今でも一般的。また、薬物試験に用いられるマウスもそうであるように、臨床試験の被験者も歴史的に男性が多い傾向があります。
イギリスで医学研究への資金提供や医療研究のサポートを行う「英国医学研究会議(Medical Research Council)」はコスモポリタンの取材に対し、「臨床試験・研究に参加する人の性別やジェンダーに関連する研究ガイドラインはまだ作成されていない」としたうえで、「しかし、我々はこれが今後の方針策定において重要な分野であることを認識しています」とコメントしました。
問題を掘り下げると、さらなる不均衡が見えてきます。イギリスでは、黒人女性の出産時に死亡する確率は白人女性の5倍であるという報告も。また、ゲイやレズビアン、バイセクシュアルの人たちは、異性愛者よりも身体的および精神的な健康問題に苦しむ確率がかなり高いほか、トランスジェンダーの人々に関しては健康に関する医療データの不足も指摘されます。マイノリティをめぐる社会的不公正の問題は長らく議論されていますが、医療の領域ではまだまだ遅れているのが現状です。
“女性であることには苦痛が伴う”?
次にご紹介するのは、子宮内膜症の診断が遅れてしまったベッカ・ファウルズさんの事例。
子ども時代、学校で授業を受けているときにお腹に原因不明の痛みを感じ、倒れこんでしまうことが少なくなかったと言うベッカさん。また、14歳の頃からは、生理のたびに大量の出血と吐き気で苦しみ、何日もベッドで過ごしていたそう。
医者の診察を何度受けても、「生理痛だから仕方がない」と言われるだけ。生理を止める様々な避妊薬を処方されたり、必要とは思えないカウンセリングを勧められたりといったことの積み重ねによって、「具合が悪いのは気のせいだと自分に言い聞かせるようになりました」と、ベッカさんは話します。
彼女が25歳になったとき、症状は悪化していました。ピルは効かなくなり、排尿時にも痛みを感じるように。医師の診察も受けても、(ベッカさん自身は絶対に違うと思ったものの)、UTI(尿路感染症)の抗生剤を処方されただけだったそう。
1年後、子宮内膜症と診断された彼女は手術を受けますが、症状は改善されず、依然として痛みはおさまりませんでした。しかし、主治医からはまたしても「(ベッカさんの)痛みは、さらなる手術が必要なほどではないはず」と言われたと言います。
それでも彼女が強く頼み込んで検査を実施した結果、膀胱に子宮内膜症があることが判明。その後、複数回の手術を受けることに。
医者は患者の痛みの程度を探るために「激痛」「鈍い痛み」「うずくような痛み」などの言葉を使ってヒアリングをすることがありますが、痛みの感じ方は人それぞれ異なるため、患者が訴えている痛みを正確に測定することは難しいかもしれません。
その一方で、ある研究は「出産機能をもつためか、女性の体は“生まれつき痛みに耐えられる能力を備えている”と思いこまれることが多い」と報告しており、こういった“誤解”が女性が受ける治療に影響を与えていると考えられます。
他にも、女性は痛みだけが理由では治療をなかなか積極的に受けない傾向があること、また、医師からも痛みについて“感情的”“心因性”“本物の痛みではない”と診断される確率が高いことを示した2001年の研究も。この研究では、男性が痛みを訴えた場合に投与される薬は鎮痛剤が多いのに対し、女性の場合は鎮静剤や抗うつ薬が多いことも指摘されています。
つまり、何世紀にもわたり、前提として“女性であることには苦痛が伴う”と考えられてきたのです。女性にとって、生理は痛いもの、性行為は痛いもの、更年期障害は辛いもの。――そしてそれに我慢できないなら、それは体ではなく心に問題があるからだということになってしまうのです。
医学部には毎年、何千人もの熱意あふれる新入生が入学します。新入生たちの生い立ちや経験は十人十色で皆違っても、誰もが偏見をもっているのです。神経科学の専門家によれば、無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)の形成は人がまだ幼い頃から始まっていると言います。医学の教育は、男性に偏った研究から得られた情報に基づいているだけでなく、既存の先入観を肯定する方法でなされているのです。
イギリスで精神科医として働くのナタリー・アッシュバーナーさんは、次のように話しています。
「医学部では多くのことを学びますが、まずパターンを把握し、共通点を見つけるよう教えこまれます。これが、治療の現場でパターンに当てはまらない一定数の患者さんの症状を見落としてしまうことにつながっていると思います」
つまり、症状がデータや研究に裏打ちされた一定のパターンに当てはまらない場合、正しい診断がなされる確率が低いということ。
「自分の思考に潜む偏見に気づく唯一の方法は『患者に自分を投影して考える』ことではないかと思っています」と語るのは、医師として働くサラ・ヒルマンさん。
「私自身、長年自分の偏見に気づくことなく診察をしてきましたが、あるとき、ふと思ったんです。『患者さんにきちんと向き合っていないな』『このままでは、ずっと平気で同じような診断ばかりしてしまうんじゃないか』って」
イギリスのNHS(国民保健サービス)では、すべての医師に対して「平等」に関する研修を実施しています。
しかし、コスモポリタンが取材した10人の医師によると、研修はたった30分のオンライン講座と最後に小テストがあるだけのもの。自分のなかにある偏見を深く掘り下げ、患者一人ひとりと向き合う方法を探る機会にはなりえません。
偏見の影響を受けるのは女性だけではない
先入観の影響を受けるのは女性だけではなく、“乳がんは女性の病気”という思い込みから男性患者の乳がんが見落とされるケースも。
もちろん、医師たちがわざと偏見にもとづいた診察をしているわけではありません。まるで息をするように自然に私たちのなかに潜む「無意識の偏見」がそうさせるのです。“外科医”と聞くと男性医師をイメージしがちで、“ヒステリックな女性”がキャラクターとしてテレビのあちこちで描かれる。--これが社会の現実なのです。
男性の場合、たとえば“男性は強くなければいけない”という固定観念に縛られて、精神的・身体的不調を感じても手遅れになるまで診察を先延ばしにし、自分で解決しようとする人が多いと考えられています。
また、かかりつけ医の診察を受ける男性は女性よりも少なく、50歳以下の男性の死因として一番多いものとして自死が挙がるほか、アルコールやドラッグに依存する傾向も男性のほうが強いとされており、危険運転が原因の交通事故を起こすのは男性ドライバーのほうが多いのです。
一方、女性にはきちんとした診断をしてもらえなかったり、最悪の場合、診断そのものをしてもらえなかったり、という傾向が。偏見はいたるところに存在していますが、医療の分野ではそれが顕著だと言えます。
AIは偏見を持たない?
イギリスの医療を支えるNHSでは現在、ジェンダーバイアスが診断内容に及ぼす影響を小さくする解決策のひとつとして、テクノロジーの活用が期待されています。AIは性別やジェンダーについての偏見をもたず、データを見誤ることがないと考えられているからです。しかし、本当にそうだと言えるでしょうか?
残念ながら、そうとも言えない事例がすでに起こっています。
2019年、ヘルスケアアプリ「Babylon(バビロン)」は、胸の痛みと吐き気を訴えた男性喫煙者に救急外来に行くよう指示した一方で、同じ年齢で同じ症状を訴えた女性に対してはパニック発作と伝えていたとして批判にさらされました。Babylon側は、Symptom Checker(症状チェック機能)は診断ツールとしての使用を想定していないこと、また、この女性に過去にパニック発作を起こした履歴があったことを挙げ、反論しました。
Babylonは膨大なデータや研究結果をもとに健康に関するアドバイスをすると言います。しかし、そもそも根拠とされるデータ自体がジェンダーバイアスがかかったものだった場合は、本来中立であるはずのテクノロジーも偏見の影響から逃れられません。
結局のところ、STEM(科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学)の分野で働く女性の比率はたったの24%だというのが現実なのです。
「STEM分野の女性研究者はいまだにあまりにも少ないです」と話すのは、ナノテクノロジーの専門家ソニア・アントランズ・コンテラさん。STEM分野により多くの女性の人材を送り込む努力を続けるソニアさんは、こう続けます。
「テクノロジーに関わる人材が多様化することにより、より良いテクノロジーの利用方法が自然ともたらされると信じています。博士号を男性だけが独占しているような状態は、テクノロジーの発展にもマイナスだと思います」
キャサリンさんやベッカさんの怒りはいまだにおさまらず、医師への不信感との戦いも続いています。キャサリンさんの場合、診断の時期によっては、手術のほかに服薬治療という選択肢もあったと考えられますし、ベッカさんも「もし膀胱の子宮内膜症が10代のうちに発見されていたなら、自分の人生はどうなっていただろうと考えてしまう」と言います。
二人に必要だったのは、医者がきちんと彼女たちの訴えに耳を傾けること。それだけだったのです。ついにその当たり前なことをしてくれる医者に出会ったとき、彼女たちが感じたのは、診断内容に悲嘆する気持ちよりも安堵だったと言います。ようやく自分たちの話を真剣に受け止めてくれる医師に出会い、ヒステリーだと決めつけられなかった、と。
「医師というのは、基本的には、人助けをしたいという思いをもつ、思いやりにあふれた人たちなんです」とアッシュバーナー博士は言います。「ストレスが原因だ」という診断が正しいときも、もちろんあるわけです。なんとなくGoogleで自分の症状を検索したりすると、根拠もない被害妄想にかられることにもなりかねません。
ヘルスケア分野にジェンダーギャップが存在すること、その解決策がまだ見いだせないことは事実です。女性の進出を増やすにも、医学部の教育内容を改革するにも時間がかかります。しかし、取り組みは始まっています。無意識の偏見が常に存在していることを意識すること、まずはこれが正しい一歩となります。偏見への非難をやめないこと、これが偏見からの影響を減らす解決策なのです。
※本記事は、Hearst Magazinesが所有するメディアの記事を翻訳したものです。元記事に関連する文化的背景や文脈を踏まえたうえで、補足を含む編集や構成の変更等を行う場合があります。
Translation:西山佑(Office Miyazaki Inc.)
COSMOPOLITAN UK