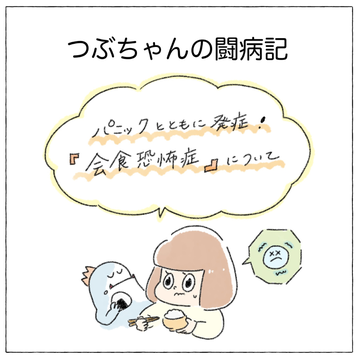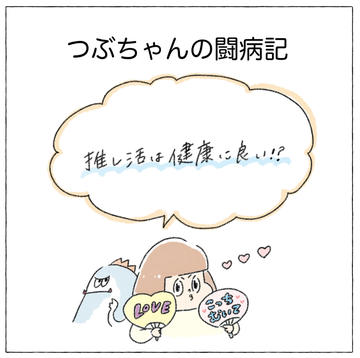イギリスを拠点に流産や死産を経験した人たちをサポートする団体「Tommy's」によれば、妊娠初期では4人に1人が流産を経験すると言います。一方で、あまり語られづらいという現状も。実際に経験するまで流産についてよく知らないというケースも少なくありません。
そこで本記事では、稽留流産(けいりゅうりゅうざん)を経験した3人の女性たちの声を<コスモポリタン イギリス版>よりお届け。人生で最も辛かったという時期とどう向き合ったのか、紐解いていきます。
稽留流産とは
稽留流産(けいりゅうりゅうざん)は、大量の出血や痛みなど、通常の流産では存在する兆候や自覚症状がないまま胎児の発育が止まっている・亡くなっているというもの。
「稽留流産は、妊婦健診で超音波検査をしたときに発覚することが多いです」と語るのは、「Tommy's」に参画している助産師のケイト・マーシュさん。それほどに、自分では気づきにくいものなのです。
サリーナさん(27歳)の場合
昨年、初めての妊娠で流産を経験したサリーナさん。流産が発覚する直前には、「何かが違う」という感覚があったと言います。
「妊娠10週目の超音波検査までの間に、何かが止まったような気がしました。とにかく、もう妊娠していない感じがしたんです。詳しく説明できないし、変に聞こえるかもしれませんが…私の中で何かがおかしい気がしました」
心配になればなるほど、長い時間を費やしてインターネットで情報を集めたものの、稽留流産の可能性を示唆するものはひとつもなかったのだとか。
「あらゆるものをチェックしましたし、『もう妊娠している気がしない』と検索してみました。でも、見つけたものすべてが“これは普通のこと”だと安心させるんです。稽留流産に類することは何も書かれていなかったので、妊娠3カ月が近づいて、私のホルモンバランスが安定してきたんだろう、という結論に達しました」
アリスさん(35歳)の場合
同じく稽留流産を経験したアリスさんにも、まるで前兆がなかったのだとか。
「当時の私はのん気で、もうすぐ12週だから安全だと思っていたんです。でも、少量の出血に気づいて、心配で検査してもらうことにしました。少しの出血はまったく問題ないこともあるので、すごく紛らわしいんですよね」
兆候がなかったために、流産だと知らされたことは青天の霹靂だったそう。「検査に行って、助産師さんが『心拍がない』と言ったときは、本当にショックでした」と、アリスさん。
「助産師さんもショックだったようです。最初は、『ああ、少しの出血ね、大丈夫』と言ってたんです。でも、さらに検査してみたら、まるで大丈夫じゃないことに気づいて」
それがどんな状況やタイミングによるものだとしても、流産や死産の経験はショックや不安を呼び起こします。
そのうえで、「稽留流産の場合は、前兆がないのがつらいところです。人々は、流産していたことを知らされるその瞬間まで気づけなかったことに、罪悪感を感じるからです」と、助産師のマーシュさんは言います。
デブラさんの場合
最近、稽留流産を経験したばかりだと言うデブラさんも、罪悪感に苛まれていると言います。
「つわりのような典型的な妊娠の兆候がないことに悩んでいました。妊娠のかたちはそれぞれで、私はただ“ラッキー”なだけと友人たちにも言われたし、インターネットで調べても大丈夫だとと思ったので、そのままにしておいたんです」
それでも不安を募らせ、検査の予約をした7週目。デブラさんは、流産したという衝撃的なニュースを聞くことになったのでした。
「その場で心が壊れてしまって、息ができなくなりました。稽留流産はとても珍しいとインターネットに書いてありました。そんなにことは自分には起こらない、と思っていたんです」
不足している「流産」についての情報
流産を経験するとき、当事者はもちろん、そのパートナーも「必死で答えを探そうとしてしまいます」と話すのは、サリーナさん。
「理由は皆ちがうし、流産の理由なんてないかもしれませんが、とにかく情報が不十分なんです」
では、なぜ流産について、とりわけ稽留流産についての情報がこれほど少ないのでしょうか。助産師のマーシュさんが指摘するのは、統計がないこと。
「イギリスでは現在、流産を記録していません。これはトミーズで改善しようと活動中なのですが、データがないと問題の大きさは隠れたままで、優先的に対処すべき問題にならないのです」
イギリス国民保健サービス(NHS)による公式の数字はないものの、トミーズの独自調査によると、流産の確立は4回の妊娠のうち1回で、その割合は30歳以下で10回に1回、35歳から39歳では10回に2回と上昇するそう。
流産が起こる原因については、「流産が最初の3カ月以内に起こる場合(いわゆる早期流産)は、最も一般的な原因は赤ちゃん自身の染色体異常です」とマーシュさん。とはいえ、残念ながら、はっきりした原因はわからないのだとか。
「なぜなら、流産についての研究は歴史的に見ても資料不足だからです。そのため多くの人々が、答えがないゆえに、自分を責めることになります」
デブラさんは、国に対して財政的な支援を求めるためにも、妊婦自身ができることがあるのかどうか知るためにも、みんなで声を上げる必要がある、と言います。
「私たちは女性として自分たちの体についてあまりに知らされていないし、私たちの医療制度は女性の健康を優先しているとは言い難いです」
「流産はよくあることですが、“普通”なことではないし、私たちはもっとよい医療を受けていいはずです。たとえばメンタルヘルスについての語られ方がまったく変わり、認知度が上がったように、流産についても同じことが起きようとしています」
当事者たちを救ったもの
人生で最もつらい時期にあったという上記の3人の女性たちを救ったのは、Tommy'sのような当事者を支援する団体や、流産を経験した人に向けた本だったそう。
「流産後の数週間は頭が真っ白で、事態を処理できませんでした」と、デブラさん。
「メンタルヘルスについてはほとんどサポートがなかった気がしました。ただ放っておかれているような感じで。共感や何かしらのガイド、答えが欲しかったけど、あると思っていたところにはなくて、とても混乱したし、孤独でした」
サリーナさんと夫のヴィックさんもまた、見捨てられたような気がしたそう。
「現場でも、メンタルヘルスやグリーフ・カウンセリング(大切な存在との死別に特化したカウンセリング)の観点からのサポートがあるべきです」
「流産の後、対応してくれた人からは気配りや寄り添う気持ちなどは感じられませんでした。ほとんど間髪を入れずに、遺体をどうするかについての書類にサインするよう求められました。それこそ、一番考えたくないことだったのに…」
この経験によって、子どもを持つことが恐くなってしまったという二人は、しばらくは子どもを持たない決断をしたのだとか。
「精神的にも肉体的にも、サリーナは深く傷ついてしまったんです」
そんな失意の日々にあって、二人が希望をみいだし、傷から癒えるための一歩をふみだせたのは、Tommy'sのような当事者たちのコミュニティがあったからだと言います。
「自分の経験を話すことで、自分の感覚は正常だと気づくことができました。ふいに怒りや失望、イライラが襲ってくるのも、すべて仕方ないことなのだと」
現在では念願の子どもを迎えたというアリスさんも、サリーナさん同様にコミュニティに支えられている一人。
「それでも私にとって、今もあのコミュニティはとても大切な場所なんです」
アリスさんは今、グループの中で、流産を経験した他の人々を支える役割を担っているそう。流産を経験したばかりの人々に向けて、「今が一番つらい時ですが、必ず苦しみが和らぐ日がきます」と語るアリスさん。
「いつか赤ちゃんを授かるとしても、たとえば養子縁組みのように、何か別のかたちをみつけるとしても、あの時よりつらいことはありません。でも、そこからの出口はきっと見つかります」
※この翻訳は、抄訳です。
Translation:mayuko akimoto
COSMOPOLITAN UK