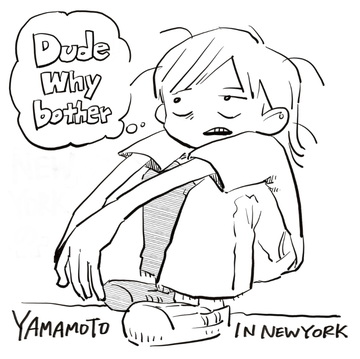レネイ・エリース・ゴールズベリーは、今や伝説といっていいほどの人気を博しているブロードウェイ・ミュージカル『ハミルトン』のアンジェリカ・スカイラー役として国際的に名を轟かせる遥か前から、ステージやテレビでキャリアを積んできた女優。
『グッド・ワイフ』や『ワン・ライフ・トゥ・リヴ』などのテレビドラマ、また『ライオン・キング』『レント』といったブロードウェイ作品で知られてきた彼女だけど、『ハミルトン』での素晴らしい演技で、ついにトニー賞受賞という偉業を達成することに。今秋で舞台出演を終えた後は、アメリカのケーブルテレビ放送局HBOが映画化する『The Immortal Life of Henrietta Lacks(原作:不死細胞ヒーラ ヘンリエッタ・ラックスの永遠なる人生)』の主演に抜擢されている45歳のヒューストン出身のレネイ。妻であり、子ども2人の母でもある彼女が、夢を追いかけて歩んで来た人生の道しるべをコスモポリタン アメリカ版に語っています。
「子どもの頃から歌が大好きでした。8歳のとき、兄と私は母に連れられてテキサス州にある夏のミュージック・シアター・プログラムに参加しました。そのキャンプで『ガイズ&ドールズ』を演じたんですが、キャンプが終わってしまうと本当に寂しくて落ち込みました。そのとき気づいたんです、自分はこれを一生やっていきたいって。
いくつもの大学に出願しましたが、その1つが世界でもトップの演劇学部があるカーネギーメロン大学でした。オーディションの準備はあまりできていませんでした。ダンステストでは、他の子たちの方が自分よりトレーニングを積んでいる姿を見て、失敗したと感じました。そのまま歌唱テストに移りましたが、歌の最中に私は試験官の女性に『もう十分です』と止められました。ショックで気絶しそうな気分で、心の中で『あー終わった。これで私は法学部進学決定だ。私の才能について、今まで周りが褒めてくれてたのは全部嘘っぱちだったんだ』とつぶやきました。その女性は私の心の声に気づいたのか、『あら、違うのよ。今の歌、本当に素晴らしかったわ』と声をかけてくれて、結果的に補欠リストに載り、そのまま入学が決定しました。
それから最高のトレーニングを受けて大学を無事卒業したわけですが、レールがしっかりと敷かれている医者や弁護士の卵と違って、パフォーマーの将来はとにかく不透明です。世界一才能があっても、努力家であっても、だからといって成功が保証されているわけではないので、なかなか苦しいものがあります。右も左もわからない私は、チャンスがあるところには何でも挑みにいきました。幸い、財政的に苦しいときは両親が支えてくれ、いつも最適なアドバイスと、きっといつか花開くと私を信じ続けていてくれました。
その後ジャズボーカルを学びに大学院に進むことを決めました。もっと勉強したかったし、ミュージカルシアターの中のシンガーとしてのみならず、1人の歌手としても自分の声と向き合ってみたかったからです。南カリフォルニア大学で修士を取得してから、レコード会社との契約を目指してL.A.に残りました。セッションの仕事をしたり、ドラマ『アリーmy love』に出演したり、トップ40ランキングに入るバンドや数々のクラブで歌ったりしていました。収入はそこそこもらっていましたが、達成感はイマイチ感じていませんでした。
20代半ばにして生まれて初めて、私は疑い始めました。自分はもしや思い違いをしていたんじゃないか?って。次のホイットニー・ヒューストンやジェニファー・ホリデーになれるんじゃないかと、大きな夢を抱いていました。しかし、他にも大勢の人が同じように考え、でも実際にそれを実現できる人はほとんどいないのだと、ここに来てやっと気づき始めました。"それでも我慢できる?""本当に成功できなかったらどうする?"そして最大の疑問は"私は自分のやるべきことを本当に全てやっているのだろうか?"ということでした。正しくない選択をして時間を無駄にしているんじゃないかと、不安で仕方ありませんでした」
「その頃ようやく『オール・アバウト・ユー』という映画の主演の仕事が舞い込み、女優の世界に戻ってきました。その裏で友達と映画音楽の作曲をし、久しぶりにクリエイティブな環境に恵まれ、満たされていました。映画祭にも出品し成功を納め、もちろんまだまだしがない若い女の子だった私でしたが、自分がこの分野に長けていることをこの身で感じていました。
この世界にいると、人生とは突然変わり得るものです。仕事がまったくないある日、電話が鳴って、次の瞬間世界の頂点に立ってしまったりする。あるいは失敗の真っただ中でも、次の大きな成功への糸を引っ張っていたりするのです。
時々ブロードウェイ・プロダクションがL.A.でオーディションを開催することがありました。『ライオン・キング』のオーディションに参加した私は、当時婚約していて、ナパ郡のブドウ畑で結婚して、一生自主映画を作り続ける予定でいました。フィアンセ(今は夫)のアレクシスは、カリフォルニア州の司法試験に合格し、弁護士になったばかりでした。結婚式の計画を進めている最中に、ニューヨークでの1年ロングラン作品で、ナラ役のオファーをもらいました。母親に電話で相談すると、『ほんの1年よ。ブロードウェイはあなたの昔からの夢だったじゃない』と言われ、私は荷物をまとめ、2匹の犬を連れて(その後夫も後から来てくれました)、1年後には再びL.A.に戻る計画でいざ出発しました。しかし『ライオン・キング』が始まって半年が過ぎた頃、昼ドラ『ワン・ライフ・トゥ・リヴ』に出演が決定し、そのままもう4年ニューヨークに残ることが確定。当時2002年でしたが、そのまま2016年現在、私は子どもたちと一緒にモーニングサイド・パーク(マンハッタンにある公園)で遊んでいます。
『ワン・ライフ・トゥ・リヴ』が始まったばかりの頃、私はとてもイライラしていました。この頃は、自分が人生で最も軽んじられているように感じていた時期でした。昼ドラの性質上、黒人が注目を浴びることはなかなか難しいのです。いつも物語の中には中心的存在の家族がいて、プロデューサーに気に入られればその家族の生き別れた兄弟役や、結婚相手役などに抜擢してもらえますが、そういった役は大体白人のもの。エスニック人種は代わりに顧問弁護士や医者などの役になるのです。となると、世間はまったく注目などしてくれません。出演だって3週間に1回あればいい方で、登場したかと思ったら一言二言セリフを言ってすぐまたハケる。それに、脚本家がその役を登場させてくれたときにしか給料は入りません。黒人は、どんなに才能があっても美しくても、トップに立つことはできない環境だったんです」
「しかし数年すると、私の役がドラマ内での三角関係にあてがわれ、状況は一転。人種の異なる配役による三角関係が描かれ、それが話題を呼びました。私のキャリアの中で、未だかつてない最高の出来事でした。雑誌に取り上げられ、ドラマファンの間で登場人物人気ナンバーワンにも選ばれました。それによりバラエティ番組『The View』の共同司会者の仕事も舞い込んで来ました。ちょうど同時期にシェイクスピア・イン・ザ・パーク(セントラル・パークで行われる野外公演)にも出演していて、ニューヨークのエリート演劇コミュニティの人たちからも驚くほど高評価のレビューをもらっていました。私の注目度は高く、周りには『やっときたね!』と言われたりもしました。それでもまだ、トップクラスからほど遠い場所にいました。
2007年に私は昼ドラの世界を後にしました。自分のキャリアにおいて次のステップへと進みたかったのです。実はそれまでの数年間、私たち夫婦は子どもを作ろうとしていました。2005年にブロードウェイの舞台の途中で流産してしまいましたが、それでも私は諦めませんでした。人生にはいつだって奇跡に対する少しの希望が必要なのです。2008年、ありがたいことに『レント』でミミ役を頂き、舞台最終日の翌日に、なんと息子ベンジャミンを妊娠していることを知りました。
2014年に初めて『ハミルトン』について聞いたとき、ラップを聞きたいと言われオーディションに出向きました。プロデューサーたちはニッキー・ミナージュタイプの人を探していて、私はまず当てはまらないだろうと思っていました。
当初はこの舞台のオーディション・ワークショップに参加することを躊躇していました。なぜなら、ワークショップに参加したからといって出演が保証されるわけではないし、家には小さな子どもが2人いるし…。しかし、(俳優の)リン・マニュエル・ミランダ氏が私の役の歌を歌ったデモ音源を聴いて、この舞台に参加しないなんてあり得ないことだとすぐに思いました。たとえ仕事がもらえなくても、このプロジェクトに投資したい。あるいはせめて関係者と友達になれないだろうか。そんなことを考えていましたが、彼らは私のお金を取るどころか、出演の仕事を与えてくれたのでした」
「トニー賞受賞で一番うれしかったのは、みなさんの前で自分の力を証明することができたことです。自分の人生って、キャリアよりもさらに必死に追いかけなければならないものなんじゃないかなと、私は思っています。子どもを作ろうと頑張っていたとき、それが私の中での一番の優先順位でした。大切なものを天秤にかけて、どちらかを失ってしまうかもしれないというリスクをいつも感じながら生きていく気持ちは私もよく分かりますが、私は家族も仕事もどちらも必死に追いかけ続け、今こうして子どもと一緒にトニー賞の受賞をお祝いできることが何よりの奇跡であり喜びです。
いつまでも光の中にいられるとは思っていません。留まる時があれば、去る時もあることを、私は知っています。今は映画スターになりたいとか、そういった野望はありません。ただ夫を愛し、子どもたちを育て、与えられたこの場所で責任を持って、授かった能力を輝かせていくのみだと感じています。そして、他に何か目指すものがあるとすれば、より一層強くたくましい女性になるということです」
※この翻訳は、抄訳です。
Translated by 名和友梨香
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がCOSMOPOLITANに還元されることがあります。